駒の価値は違う。ある程度は感覚的に理解できると思う。
もちろん状況によって駒の価値が変わる。
序盤では手得より歩得というくらい駒得が大事。
中盤以降はそういうことではない。
今回は古い棋譜で考えてみたい。
激しい変化のなかで駒の損得を考えてみる。
表題:駒の損得
先手:塚田 正夫
後手:木村 義雄
▲7六歩 △3四歩 ▲2六歩 △5四歩 ▲2五歩 △5五歩
▲2四歩 △同 歩 ▲同 飛 △3二金 ▲3四飛 △5二飛
▲2四飛 △5六歩 ▲同 歩 △8八角成 ▲同 銀 △3三角
▲2一飛成 △8八角成 ▲7七角 △8九馬 ▲1一角成 △5七桂
▲5八金左 △5六飛 ▲6八桂 △4九桂成 ▲同 玉 △5八飛成
▲同 玉 △6二玉
*ほとんど定跡化されている手順。
*先手やや有利。
*このような激しい駒の取り合いがある将棋では、一段落した局面(この
*△6二玉)で損得計算
*をすればよい。
![]()
▲5三歩 △7二玉 ▲5五馬 △5四歩 ▲同 馬 △6四金
▲3六馬 △5七歩 ▲同 玉 △8二玉 ▲6六香
*先手磐石の体制となった。
*この結果、4勝2敗1持将棋で塚田名人が誕生した。
![]()
この時点では先手がはっきり駒得で駒の働きまで良い。
金銀の数が後手が圧倒している。穴熊のような展開ならそういうやり方がセオリー。
だが、ここでは後手苦しい。
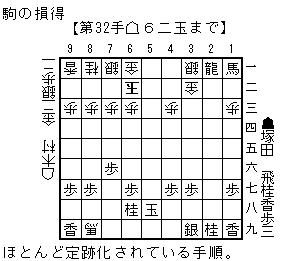

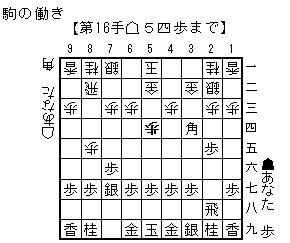
コメント